ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2020年12月号記事 vol.199 ヨガの健康効果
2020年12月号記事 vol.199 ヨガの健康効果健康への効果が高いとされるヨガ。近年、在宅の時間が長くなり、自宅で手軽にできる健康方法として関心が高まっています。今回は、ヨガの心や身体への健康効果について米国からのレポートをご紹介します。 ヨガとピラティスの健康効果、糖尿病や高血圧患者にも-米専門家がアドバイス 美容や健康の維持に有効なエクササイズとして人気な「ヨガ」と「ピラティス」は、特別な器具をほとんど必要とせず、一度習得すれば自宅で安全に行えるという特徴があります。米ペンシルバニア州立大学ミルトンS. ハーシー医療センターのスポーツ医学を専門とするJayson Loeffert氏は「ヨガとピラティスはどちらも、自分の体力に合わせて初心者から上級者レベルまで運動強度を自由に変えられるという利点がある」と強調。低強度な運動であるため、糖尿病や高血圧といった慢性疾患患者にも有用だとしています。Loeffert氏は「初心者は […]
-
 2020年11月号記事 vol.198 緑豊かな環境が心血管疾患や子供の免疫改善に効果?
2020年11月号記事 vol.198 緑豊かな環境が心血管疾患や子供の免疫改善に効果?森や山で、草地などの自然が豊かな場所に行くと、ホッとリラックスし、身体も心も元気になりそう…、そんな気分になった経験はないでしょうか?今回は、自然豊かな環境が健康にもたらす効果を米国とフィンランドの研究からレポートします。 緑豊かな環境が心血管疾患による死亡を減らす? 木々や草地などの緑のある空間が増えると、大気の質が改善され、心血管疾患(CVD)による死亡リスクが低下する可能性があるとする研究結果を、米マイアミ大学ミラー医学部のWilliam Aitken氏らが発表しました。詳細は、米国心臓協会学術集会(AHA Scientific Sessions 2020、11月13〜17日、バーチャル開催)で発表されました。 大気の質は健康に影響を与える主要な環境因子です。そこでAitken氏らは、2014〜2015年の米疾病対策センター(CDC)の報告による米国でのCVDによる死亡 […]
-
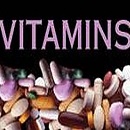 2020年10月号記事 vol.197 風邪の予防やつらい症状に
2020年10月号記事 vol.197 風邪の予防やつらい症状に日に日に寒さが増し、風邪をひきやすい季節になってきました。日常生活の中で、いろいろな予防方法を心掛けている方も多いのではないでしょうか。今回は、風邪の予防について、英国と米国のレポートからご報告します。 ビタミン摂取で風邪を予防できる? ビタミンA、D、Eの摂取量が多い人は、風邪をひきにくい可能性があるとする研究結果を、英インペリアル・カレッジ・ロンドン(ICL)のSuzana Almoosawi氏らが、「BMJ Nutrition, Prevention & Health」2020年10月27日オンライン版に報告しました。この研究は、英国の調査「National Diet and Nutrition Survey Rolling Programme (NDNS RP)」に2008~2016年に参加した、19歳以上の成人6,115人を対象としたものです。対象者は、3日 […]
-
 2020年9月号記事 vol.196 怒りやストレスと健康
2020年9月号記事 vol.196 怒りやストレスと健康怒りや過度なストレスは、精神状態だけでなく健康にも望ましくない影響があることは、これまでも指摘されてきました。今回は、攻撃性や怒り、ストレスなどの感情による健康へのリスクについてのレポートをご紹介します。 攻撃性が心筋梗塞の再発リスクを高める? 怒りっぽい態度は、2度目の心筋梗塞を起こすリスクを高める可能性のあることが、「European Journal of Cardiovascular Nursing」2020年9月14日オンライン版に掲載された論文で明らかにされました。 急性冠症候群(ACS)は、冠動脈のプラークが破れて血流が悪くなったり詰まったりすることで生じる病態で、臨床的には、急性心筋梗塞、不安定狭心症、心臓突然死を指します。この研究は、ACSの既往歴を有する患者2,321人を対象として24カ月にわたって追跡し、攻撃性がACSの再発またはACSによる死亡の予測因子 […]
-
 2020年8月号記事 vol.195 気候変動は健康にも影響する
2020年8月号記事 vol.195 気候変動は健康にも影響する近年、地球の気候変動が大きな問題となっています。今回は、このような気候変動が私達の健康に及ぼす影響について、アメリカのレポートからご報告します。 「気候変動と戦おう」米国の内科医ら呼びかけ 米国内科学会(ACP)は、「温暖化と天候パターンの変化により関連する疾患が増加し、人々の健康が蝕まれつつある」との声明を発表しました。同学会では、温室効果ガスの排出を抑えることで、気候変動と戦うことを呼びかけています。同学会会長のWayne Riley氏は、「地球温暖化に伴い、呼吸器疾患や熱射病、感染症が増加している。気候変動への対処を始めないと、こうした健康被害はますます増えるだろう」と述べています。詳細は「Annals of Internal Medicine」オンライン版に2016年4月19日に掲載されました。 同学会では、気温上昇により、オゾン汚染、山火事の煙、牧草や樹木などから生 […]
-
 2020年7月号記事 vol.194 植物性タンパク質の摂取は長生きの秘訣?
2020年7月号記事 vol.194 植物性タンパク質の摂取は長生きの秘訣?肉や卵などの動物性タンパク質よりも、大豆などの植物性タンパク質を多く摂取した方が健康には望ましいことは以前から指摘されていますが、健康だけでなく環境にも優しいようです。今回は、食生活の中で、動物性タンパク質を植物性タンパク質に置き換えていくことのメリットについて、健康と環境の側面から米国のレポートをご紹介します。 朝食には卵の代わりに豆腐を食べ、料理には牛肉ではなく豆を使うようにすれば長生きできるかもしれない―。そんな研究結果を、米国立がん研究所(NCI)のJiaqi Huang氏らが「JAMA Internal Medicine」2020年7月13日オンライン版に発表しました。普段の食事中の動物性タンパク質を植物性タンパク質に置き換えると、全死亡リスクが低下する可能性があることが明らかになりました。 Huang氏らは今回、1995年から2011年にかけて、食事パターンと健康に関する長期的 […]
-
 2020年6月号記事 vol.193 支配的な親を持つティーンは成人後に苦労する?
2020年6月号記事 vol.193 支配的な親を持つティーンは成人後に苦労する?ティーンの子どもを持つ親は、子どもから少し距離を置くことも必要かもしれません。親が支配的だと感じているティーンは、自主性が育ちにくく、大人になったときに恋愛関係を築くのが難しくなる可能性が高いとする研究結果を、米バージニア大学のEmily Loeb氏らが報告しました。同氏は「この研究で因果関係が証明されたわけではないが、過干渉な育て方は、子どもにとって有害無益であることを示す新たなエビデンスとなるものだ」と説明しています。研究論文は「Child Development 6月16日オンライン版に掲載されました。 この研究は、さまざまな社会経済的背景を持つ男女184人を13歳のときから32歳になるまで追跡調査したもので、Loeb氏らは、対象者が13歳のときに質問票を用いて、親による支配の状況や自身の心理社会的成熟度、抑うつ症状などについて回答してもらいました。また、彼らが抱えている何らかの問題 […]
-
 2020年5月号記事 vol.192 「気候非常事態」に世界の科学者らが警鐘
2020年5月号記事 vol.192 「気候非常事態」に世界の科学者らが警鐘地球は「気候の非常事態」に直面しており、思い切った方策をとらなければ人類に計り知れない苦難がもたらされることになる――。そう主張する研究論文が、「BioScience」2019年11月5日号に発表されました。この論文には世界153カ国の科学者1万1,258人が賛同し、共同署名しています。今回は、地球温暖化によって私達が直面する問題について、米国のレポートからご紹介します。 前述の論文の筆頭著者である米オレゴン州立大学教授のWilliam Ripple氏は、「気候変動による地球温暖化は飢餓や疾患を劇的に増加させ、既に人々の健康に打撃を与えている」と説明。気候変動は多くの科学者の予測よりも早い段階から始まり、急速に進行し、その影響は極めて深刻なものだということです。 温暖化による感染症の拡大 また、米ノースウェル・ヘルスのEric Cioe Pena氏も「地球温暖化が既に人々の健康に影響を与え […]
-
 2020年4月号記事 vol.191 「音楽療法」に期待される様々な効果
2020年4月号記事 vol.191 「音楽療法」に期待される様々な効果音楽は気分を高めたり、ストレスを和らげたり、時には気分転換や癒しになったり、日々の生活の中で、様々な形で私達に関わっていて、その効果から健康にも役立つと考えられています。今回は、音楽の健康に対する効果について、海外のレポートからご紹介します。 「音楽療法」が心筋梗塞後の不安や痛みを軽減する 音楽は、心臓にも良い影響を与えるという研究があります。音楽を1日に30分間聴くと心筋梗塞後の胸痛や不安が軽減するという研究結果を、ベオグラード大学(セルビア)のPredrag Mitrovic氏が、米国心臓病学会と世界心臓病学会の合同オンライン会議(ACC/WCC 2020、3月28~30日)で発表しました。同氏は「音楽療法は簡単かつ安価に行える上、心筋梗塞を起こした全ての患者に有用だと思われる」と述べています。 米国では、心筋梗塞から回復した患者のうち約9人に1人は、心筋梗塞の発症から4 […]
-
 2020年3月号記事 vol.190 筋肉量を維持するために継続的な運動を
2020年3月号記事 vol.190 筋肉量を維持するために継続的な運動を「運動は無理なく継続することが大切」と言われますが、運動を継続することは健康にどのように影響を与えるのでしょうか。また、あまり無理をすると継続することが難しくなってしまいますが、手軽に継続するためにはどのような方法が考えられるのでしょうか。英国と日本のレポートからご紹介します。 座りがちな生活で筋肉量が減少 わずか2週間、身体活動を控えて座りがちな生活を送るだけでも、健康な若者が筋肉を失い、内臓脂肪がつき始めるとの研究結果が報告されました。結果的には心疾患や2型糖尿病のリスクが高まり、早期死亡に至る可能性があるということです。この研究結果はポルトガルで開催された第24回欧州肥満会議(ECO 2017)で2017年5月17日に発表されました。研究を率いた英リバプール大学加齢・慢性疾患研究所のKelly Bowden-Davies氏は、「本研究で注意すべき点は、被験者が健康なボラ […]
-
 2020年2月号記事 vol.189 歯の健康と全身の健康
2020年2月号記事 vol.189 歯の健康と全身の健康近年、歯の健康が全身の健康に影響することが様々な観点から指摘されています。それでは大切な歯を守るためにはどのようなことに気を付けると良いのでしょうか。今回は、日本と米国の研究を中心に、歯の健康についてのレポートをご紹介します。 「喫煙、糖尿病、骨粗鬆症」で歯の喪失リスク増 日本人の高齢者では、喫煙習慣と糖尿病、骨粗鬆症が歯を喪失するリスク因子である可能性があると、敦賀市立看護大学(福井県)の中堀伸枝氏と富山大学教授の関根道和氏らの研究グループが「BMC Public Health」2019年6月4日オンライン版に発表しました。 歯周病などの口腔衛生と食生活や喫煙などの生活習慣は、高齢者が歯を喪失するリスクを高めることが報告されています。同調査は、同県在住の65歳以上の高齢者1,537人を無作為に抽出し、同意が得られた1,303人(回答率84.8%)を対象としたものです。今回の […]
-
 2020年1月号記事 vol.188 緑茶をよく飲む人は長生きできる?
2020年1月号記事 vol.188 緑茶をよく飲む人は長生きできる?日本人に馴染みが深く、健康にも良いと言われる緑茶。今回は、緑茶の健康効果について、中国と日本の最新の研究をご紹介します。 緑茶をよく飲むと長生きできる? 緑茶をよく飲む人は健康で長生きできる可能性が高いことを示唆する大規模研究の結果が報告されました。中国医学科学院のXinyan Wang氏らが10万人超の中国の成人を対象に実施した研究で、研究結果の詳細は、「European Journal of Preventive Cardiology」2020年1月8日オンライン版に掲載されました。 この研究は、中国における動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)リスクの予測を目的とするプロジェクト(China-PAR)に登録された中国の成人10万902人を対象に解析しました。研究チームは質問票を用いて、対象者の飲茶習慣のほか、生活習慣や病歴などに関する情報を集めるとともに、体重、血圧、コレ […]
