ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2007年12月記事 vol.43 色の作用で心身を癒す、カラーセラピー
2007年12月記事 vol.43 色の作用で心身を癒す、カラーセラピー色が持つそれぞれ特有の波長で心と体が癒されると注目のカラーセラピー。不眠やストレスの解消、精神の鎮静化など代替医療としても有効性が立証されつつある。最近では、アロマやヨガとの組み合わせでより効果を高める利用法も工夫されている。カラーセラピーの現況を報告する。 古代エジプトでも医療に使われていた トレンディーなスパやヨガスタジオなどで利用され、オシャレなイメージのあるカラーセラピー。その起源は古代文明までさかのぼる。 古代エジプトでは、色のついたガラスの部屋に日光を取り込み、患者たちはそこで色の波長に包まれるようにして、体調を整えたといわれる。 古代中国やインドでも色を用いた施術があり、現在も古代インド医学のアーユルヴェーダとの組み合わせで使われるなど用途は幅広い。 ヨーロッパでは19世紀、天然痘やはしかの治療に赤い部屋を使っていたといわれる。また、アメリカでも19世紀半ば頃から代替医療の […]
-
 2007年11月記事 vol.42 50歳以上のアメリカ人、7割が代替医療を利用 米国NCCAM(代替医療調査センター)報告
2007年11月記事 vol.42 50歳以上のアメリカ人、7割が代替医療を利用 米国NCCAM(代替医療調査センター)報告アメリカで2007年6月、日本では8月25日から公開されたマイケル・ムーア監督の「Sicko」。前作「華氏911」では、同時多発テロでのブッシュ大統領の行動を批判したが、今回は米国の医療制度の闇に切り込んだ。90年代に入って、代替医療が注目、さらに統合医療へと向かう米国の現況を報告する。 無保険者を中心に、代替医療への関心高まる 「Sicko(シッコ)」の制作にあたり、ムーア監督は、Webサイトで米国医療制度の問題点を募り、寄せられた内容をもとにドキュメンタリータッチで映画を仕上げた。米国だけでなく、イギリス、フランス、カナダなどの医療システムも取り上げている。 映画では、ニューヨーク9・11テロで復旧に当たり、粉塵吸引が原因と見られる呼吸器疾患に苦しむ元作業員を紹介。無保険者で満足のいく治療が受けられないため、彼をキューバの医療施設へと連れていく。 ムーア監督は「キューバ […]
-
 2007年10月記事 vol.41 メディテーションで認知力の向上が立証
2007年10月記事 vol.41 メディテーションで認知力の向上が立証メディテーションで認知症患者の記憶・認知力が向上する――。今年6月、米国でメディテーションの効用が科学的に立証された。毎日わずか10数分のメディテーションで、それが期待できるという。すでに、医療分野への応用も試みられている。注目されるメディテーションの効用とは。 アルツハイマー協会もメディテーションの効果に期待 今年6月、ワシントンDCでアルツハイマー協会主催の認知症予防に関する国際会議が開かれた。そこで、ペンシルベニア大学医学部が「メディテーションによる認知力の向上」を立証する研究結果を報告、大きな話題を呼んだ。 研究は、認知障害を訴える、あるいは軽度の認知症と診断された患者、52歳から70歳に、記憶・認知力のテストを実施、SPECTスキャンで脳の血流状態を調べた。 被験者は、1970年代にインド人のヨギ・バジャン師(1929-2004)がアメリカで広めたクンダリーニ・ヨガのメディテー […]
-
 2007年9月記事 vol.40 関節炎や痛みの緩和で人気、水療法
2007年9月記事 vol.40 関節炎や痛みの緩和で人気、水療法先進諸国では、高齢者の増加から膝関節のトラブルなどが増えることが予想される。そうした関節炎の痛みを緩和し、血液循環を促す水療法(ハイドロセラピー)が人気だ。その効用を探る。 ドイツの宗教家が注目、「クナイプ療法」として有名に 水療法(Hydrotherapy=ハイドロセラピー)の発祥は、紀元前2000年頃まで遡る。 その頃すでに、水や湯の身体に与える作用が認知され、さまざまな疾患の治療やリハビリに利用されていたといわれる。 19世紀の終わり頃、ドイツの宗教家、セバスチャン・クナイプが水療法に注目、著書『My Water Cure』(1886年)の中で紹介し、「クナイプ療法」として広く知られるようになる。 水治療は特にヨーロッパで好意的に受け入れられ、スパに取り入れられたり、専用施設も開設された。 特に、18~19世紀は建設ラッシュで、眺望の良い丘や湖の近くに多く造られた。施設には、患者の […]
-
 2007年8月記事 vol.39 膵臓がん治療でNIH(米国立衛生研)も期待、ゴンザレス療法
2007年8月記事 vol.39 膵臓がん治療でNIH(米国立衛生研)も期待、ゴンザレス療法がんのなかでも、とりわけ治癒率が低いとされる膵臓がん。これに食事療法で挑むという試みが注目されている。「膵酵素はがんを殺す」という研究理論に基づいた食事療法、ニューヨークの医師ニコラス・ゴンザレス博士が開発したゴンザレス療法だ。米国立衛生研究所(NIH)の代替医療部門(NCCAM)も研究資金を提供し、有効性の科学的立証に期待をかけている。 NIH、研究資金140万ドルを提供 膵臓がんは、米国におけるがん死亡原因の第5位。他の器官へ転移のない初期段階で発見されるケースは20%とごくまれである。 初期段階で腫瘍を完全に切除しても5年生存率は約20%と低い。末期の5年生存率は1%を切り、1年以内に死亡する患者がほとんどという。 極めて治癒率の低い膵臓がんだが、進行膵臓がん患者11人を対象に、膵酵素と食事療法を併用するというゴンザレス療法を試みたところ、平均生存率は17ヵ月半で、なかには5年近く […]
-
 2007年7月記事 vol.38 想像力で身体機能をパワーアップ、イメージ療法
2007年7月記事 vol.38 想像力で身体機能をパワーアップ、イメージ療法多くのアスリートが、勝利を手にするため、試合前に理想的なフォームやゲーム運びをイメージするといわれる。近年、イメージにより自身の身体機能を理想的なものへと導き、体力の向上や病気の治療などに役立てようとする試みが注目されている。イメージ療法の効用とは。 イメージで心と身体を調整、病気治療に役立てる 頭の中で山や川などの雄大な景色を思い描くと、心が落ち着き、体がリラックスしてくる。これを病気の治療に応用したのがイメージ療法である。 記録によると、こうした技法は、遡って古代のバビロニアやギリシャ、ローマ時代にも見られるといわれる。 イメージ療法には様々な技法があるが、中でも「コーミング」と呼ばれるテクニックが人気を集めている。これは、手で両目を押さえ、不安感やストレスを掻き立てる色(赤など)、続いてリラックスや落ち着きを表す色(青など)をイメージしていくというもの。 また、胸の辺りで優しいヒー […]
-
 2007年6月記事 vol.37 オーガニック果物・野菜で体内浄化、ゲルソン療法
2007年6月記事 vol.37 オーガニック果物・野菜で体内浄化、ゲルソン療法米国でマクロビオティックとともに、がん予防や治療の食事療法として知られるゲルソン療法。オーガニック果物・野菜のジュースやサプリメントを用い、体内浄化に努め、自然治癒力を高める。がん治療に効果的なケースもみられるものの、一方で、権威ある医療機関から有効性の科学的検証を求められている。ゲルソン療法の現況を報告する。 がんの治療や再発防止の食事療法として広まる ゲルソン療法は、ドイツからアメリカに移住したマックス・ゲルソン医学博士が1930年代に開発した食事療法。当初、ゲルソン氏が自身の偏頭痛治療に用いていたといわれる。後に、結核治療にも利用、さらに、がんの治療や再発防止の療法として広まっていく。 ゲルソン療法では、体内に毒素が溜まることで、細胞のメタボリズムに障害が生じ、がんが発症するとしている。解毒を担う肝臓も負担が高まる。そのため、がんの誘発に関わると思われる食品を排除し、栄養素をバラン […]
-
 2007年5月記事 vol.36 言葉で心の重荷を払う、トークセラピー
2007年5月記事 vol.36 言葉で心の重荷を払う、トークセラピー競争社会アメリカでは、5人に1人がストレスや何らかの精神的疾患を抱えているといわれる。リラックス関連サプリメントの人気は依然根強い。そうした中、うつ病などへの対策として、薬剤治療の他に「トーク セラピー」が注目を集めている。トーク セラピーの効用とは。 「認知」「行動」「対人関係」のステップで、心を軌道修正 トーク セラピーとは、心の重荷になっている事柄を言葉で取り除くというもの。第三者に話すことで、冷静に自己を見つめ、自身では気づかなかった心の病への対処方法がわかる。 トーク セラピーには3つのステップがある。まず「認知療法」。一人ひとりの自己認識の歪みを、客観的な視点から修正していく。 次に「行動療法」。問題となる行動を望ましいものへと正す。そして「対人関係療法」。他者への感情表現や上手な対応を学びながら、人との良好な関係構築を図る。 うつ病への有効性が報告 University o […]
-
 2007年4月記事 vol.35 地中海ダイエットのヘルシー効果、相次ぎ報告
2007年4月記事 vol.35 地中海ダイエットのヘルシー効果、相次ぎ報告地中海ダイエット(地中海式食事)のヘルシー効果が注目されている。小児ぜんそくからアルツハイマー病の予防までさまざまな効用が相次いで報告され、アメリカの健康業界では「全穀ブーム」に次ぐ新たなトレンドとして話題を呼んでいる。地中海ダイエットの効用とは。 オリーブオイルをベースに、果物や野菜、穀物、魚介類を多く摂る 今年4月初旬、ロンドンのNational Heart and Lung Instituteの研究チームが、小児ぜんそくに関する研究成果を報告した。 それによると、ギリシャのクレタ島に住む7歳から18歳の子供約700人を対象にした調査で、フルーツや野菜を主に食べている子供は、そうでない子供に比べぜんそくなどの呼吸器系疾患のリスクが低いことが分かったという。 また、豆類を少なくとも週に3回食べている子供も、ぜんそくのリスクが低かったという。さらに、 マーガリンをよく食べる子供は食べない […]
-
 2007年3月記事 vol.34 栄養成分を静脈内に注入、IVMT
2007年3月記事 vol.34 栄養成分を静脈内に注入、IVMT栄養素を多量に投与して治癒力を高める治療法に関心が集まっている。その一つ、静脈内へ直接栄養素を注入するIntravenous Micronutrient Therapy(IVMT)も、現在、米国内で1,000人以上の医師が利用しているという。IVMTの効用とは。 米国代替医療研究機関(NCCAM)でも研究対象に Intravenous Micronutrient Therapy(IVMT)は、通常経口で摂取する栄養素を直接静脈内に注入するというもの。 栄養成分が消化器官で酵素変換などの影響を受けないため、吸収効率が良いと考えられている。 消化器系や口内に疾患を持つ患者への栄養投与にはうってつけで、現在、米国の代替医療研究機関(NCCAM:National Center for Complementary and Alternative Medicine)でも研究対象となっている。 IVM […]
-
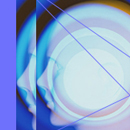 2007年2月記事 vol.33 マインドパワーで身体を癒す、バイオフィードバック
2007年2月記事 vol.33 マインドパワーで身体を癒す、バイオフィードバック心のパワーで身体の病を癒すバイオフィードバック。喘息にADHD(注意欠陥・多動性障害)にと効用も幅広く、取り入れる医療施設が増えている。バイオフィードバックの効用とは。 測定器を使い、呼吸法や瞑想などで体の調子を整える 「BIO」は「生体」、「FEEDBACK」は「情報を返す」の意。バイオフィードバックは、マインドでボディーをコントロールする、今話題のマインド・ボディー・セラピーのひとつだ。 心拍数、血圧、体温、脳波、筋肉の緊張度などをチェックする測定器を体につけ、モニターを見ながら身体の状態を把握する。モニターからリアルタイムでフィードバックされる生体情報をもとに、専門家のアドバイスを受けながら、リラクゼーションやイメージなどのテクニックを用い身体の状態を意識的に調節する。 たとえば、緊張からくる頭痛の場合、筋肉がどのように緊張しているかをモニターで確認し、緊張からリラックスへと転換す […]
-
 2007年1月記事 vol.32 気血の流れを調整、ポラリティセラピー
2007年1月記事 vol.32 気血の流れを調整、ポラリティセラピーおよそ60年前、アメリカの一医師が提唱したポラリティセラピーが、代替医療ブームの中で広がりをみせている。ストレッチに指圧に呼吸法、さらにポジティブ思考や栄養摂取まで取り入れトータルな観点から健康作りを目指す。ポラリティセラピーとは。 生体エネルギー、気血のバランスを整える ポラリティ セラピーとはホリスティック医学の一つで、人体に流れるエネルギー、気血のバランスを調整する療法である。ポラリティとは、プラス(陽)とマイナス(陰)の「極性」を意味する。 人の健康は、体の中でエネルギーがスムーズに流れることによって保たれる。この流れが滞り、生体や気血バランスが崩れると、ストレスやこり、痛み、疾患となって現れる。 この滞りを取り除き、本来の気血の流れに戻すことで、人が元々持つ自然治癒力が高まり、健康が促進される。これがポラリティ セラピーの理論である。 1984年、全米ポラリティ セラピー協会設 […]
