ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
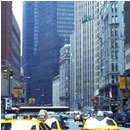 2011年12月記事 vol.91 大豆の健康効果、米国民の8割が認知
2011年12月記事 vol.91 大豆の健康効果、米国民の8割が認知アメリカに「大豆」ブームが到来して10年。大豆に含まれるさまざまな栄養素や有効成分がアメリカ人に認知され、大豆食品はヘルシーフードの代表格として市場を牽引してきた。アメリカにおける大豆食品市場の近況を報告する。 今年8月、United Soybean Boardが発表した統計によると、アメリカの消費者の81%が「大豆は体に良い」と信じており、「健康を害する」と思っている人はわずか5%であることが明らかになった。 また、少なくとも月に1度は大豆関連の食品や飲料を消費者の37%が購入しており、2008年に比べると5%上昇していることも分かった。 アメリカでヘルシーな食品として国民の間にすっかり定着した豆腐や豆乳などの大豆食品。米国食品医薬品局(FDA)が1999年に大豆ベースの食品や飲料に心臓病予防効果の表示を認めたことから、大豆ブームが巻き起こった。 しかし、今年4月のミンテルの調査報告は […]
-
 2011年11月記事 vol.90 米国民の9割、機能性食品を信頼
2011年11月記事 vol.90 米国民の9割、機能性食品を信頼ヘルシーエイジング志向の高まるアメリカで、体に良い成分の含まれる機能性食品が着実に市場規模を広げている。肥満、ストレス、活力アップで機能性食品を求める消費者は少なくない。機能性食品への消費者の意識、市場規模など最新状況を報告する。 アメリカ人の5人に1人が抗老化に強い関心 食品には「栄養」、「おいしさ」、「病気の予防」の3つの役割がある。そのうち「病気の予防」に焦点を当てているのが機能性食品である。 コンセプトは、免疫、分泌、神経、循環、消化といった生体調節機能により病気を予防する働きのある食品で、シリアル、ブレッド、ヨーグルト、スナック、飲料などがある。 インターナショナル・フーズ・インフォメーション・カウンシル(IFIC)の「2011年機能性食品・食品における健康意識調査」によると、アメリカ人が最も関心の高い健康上の問題は、トップが心臓疾患で46%、次いで体重が32%、ガンが22%と […]
-
 2011年10月記事 vol.89 米国不況で、さらに高まるセルフケア志向
2011年10月記事 vol.89 米国不況で、さらに高まるセルフケア志向景気低迷が続く米国、節約のため「医者になるべくかからないように」とアメリカ人の間でセルケア志向が高まっている。体に良いとされる食べ物やサプリメントで病気予防を心がけ、ちょっとした病気なら医者に頼らず自然な代替医療で治す。そうした風潮が広がっている。 増える無保険者、下がる中間世帯年収 ニューヨークのウォール街で始まった反格差社会デモ。多くの富を手にし、政治に多大な影響を及ぼす超富裕層1%に対し、99%の一般市民が「富の公平な配分」を訴え、怒りを爆発させた。 米国勢調査局によると、昨年の世帯年収の中央値は4万9千445ドルで、前年に比べると2.3%の下落。総人口のうち貧困層の占める割合は前年の14.3%から15.1%へと跳ね上がった。つまり6~7人に1人が貧困層ということになる。 ちなみに、米国では4人家族で年収約2万2千ドル以下を貧困層と定義している。 健康保険に加入していない人も前年の […]
-
 2011年9月記事 vol.88 米国でヘルシーな食生活を望む国民が増加
2011年9月記事 vol.88 米国でヘルシーな食生活を望む国民が増加ヘルシーな食生活で健康を―。そう望むアメリカ人が年々増えている。ところが、不況の影響で「健康」よりも「値段」が優先、ヘルシーでなくても、安ければ買ってしまうことに。そんな理想と現実のギャップが浮き彫りになった2つの調査報告が発表された。 「食生活と健康に密接な関係があると信じている」が86% 健康業界専門のマーケティング会社Natural Marketing Institute(NMI)がつい最近、2010年Health and Wellness Trends Databaseの調査報告を発表した。 それによると、アメリカ人の86%が「食生活と健康に密接な関係があると信じている」と答えており、年々健康志向が高まっていることが明らかとなった。 以下、「ヘルシーな食品と飲料水は生活の質の向上に役立つと信じている」が81%(09年は78%)、「健康な食生活で自分の人生をコントロールできる と信 […]
-
 2011年8月記事 vol.87 ヘルシー・エイジング、若年層で高まる「若さ維持」願望
2011年8月記事 vol.87 ヘルシー・エイジング、若年層で高まる「若さ維持」願望年を重ねてもいつまでも若々しく、エネルギッシュでいたい。米国でそうしたヘルシー・エイジングへの関心が若者の間で高まっている。背景には、生活習慣病の発症が若年化していることがありそうだ。今回は、米国における若年層のヘルシー・エイジング願望の現状を報告する。 生活習慣病の発症が若年化 生活習慣病の代表格といえば、高血圧に高コレステロール、そして糖尿病。今年4月、こうした疾患の発症率を年齢別に調べた興味深いデータが発表された。 ギャラップ調査の「Healthways Well-Being Index」で、2009年-2010年にかけ、18歳以上のアメリカ人約65万人を対象に生活習慣病の実態調査を行った。 結果、「医者から高血圧または高コレステロール、糖尿病と診断された」と答えた人の内訳は、高血圧が31%、高コレステロールが27%、糖尿病が11%であった。 これを年齢別でみると、高血圧の発症は、 […]
-
 2011年7月記事 vol.86 米国における代替療法利用の現状 50歳代が最も多く利用
2011年7月記事 vol.86 米国における代替療法利用の現状 50歳代が最も多く利用先頃、米国における代替療法の利用についての調査結果が発表された。50歳以上のアメリカ人を対象にした調査で、ベビーブーマー世代(団塊の世代)を中心に、ハーブやサプリメントによる栄養療法の利用者が増えている状況が明らかになった。 ベビーブーマー世代の過半数がハーブやサプリメントを利用 シニア支援を目的とする全米最大規模の非営利団体「AARP」と米国補完代替医療センター(NCCAM)が昨年10月、50歳以上のアメリカ人1,013人を対象に代替療法の利用について聞き取り調査を実施。先頃、調査結果が発表された。 調査によると、53%がこれまでに何らかの代替療法を利用、この1年以内にも47%が利用しており、女性が51%で男性の43%を上回っていることが分かった。 さらに、高学歴ほど、ハーブやサプリメント、マッサージなどの代替療法を利用する人々が増えていることも明らかになった。 ちなみに、自然療法、鍼 […]
-
 2011年6月記事 vol.85 健康の「食品ピラミッド」、プレート型に一新
2011年6月記事 vol.85 健康の「食品ピラミッド」、プレート型に一新健康的な食生活のための「食品ピラミッド」が、食卓の皿をモチーフにしたデザインに一新された。「マイプレート」と呼ばれ、シンプルで覚えやすく、子どもから大人まで毎日の食生活に活用できるようなイメージになっている。 シンプルにわかりやすく、食品群を分類 1992年、米農務省は1日に必要な食品群をイラスト化した「食品ピラミッド」を考案した。 2005年にはこれを改め、栄養素と食物を分類、また運動の重要性も示すなど工夫を凝らしたが、複雑で分かりにくく、子どもたちが理解するのは到底無理と不評を買っていた。 そこで今年1月に発表された「2010年アメリカ人のための栄養ガイドライン」に合わせ、6月2日、農務省は健康的な食事の目安となる「マイプレート」を発表。 誰もが理解できるような、シンプルさを重視した新デザインをアピールした。 「マイプレート」では、1枚の皿を4つの食品群に分割。食品分類では、野菜と果 […]
-
 2011年5月記事 vol.84 米国団塊の世代、メディカル・フードに注目
2011年5月記事 vol.84 米国団塊の世代、メディカル・フードに注目ナチュラル志向で薬嫌い。そんな米国のベビーブーマー世代(団塊の世代)が加齢に伴い、メディカル・フードに関心を寄せている。米国食品医薬品局(FDA)が医薬品と栄養補助食品の中間に位置付けるメディカル・フード。高齢者人口の増加を背景に市場は拡大の一途を辿りそうだ。 米国で、毎日約1万人が65歳以上の高齢者に 1946年から1964年の間に生まれたベビーブーマー世代。今年、この世代の第一陣が米国で高齢者とされる65歳になる。 米国のどこかで、毎日約1万人が65歳の誕生日を迎え、13秒ごとに高齢者が誕生することになる。しかもこの人口推移は今後18年にわたり続くことになる。 ヘルス志向が強いベビーブーマー世代だが、加齢に伴いさまざまな慢性疾患に悩む人も少なくない。これまでのグルメ生活のツケがまわって肥満や糖尿病、メタボリックシンドロームといった生活習慣病を発症している。 この世代にはオーガニックや […]
-
 2011年4月記事 vol.83 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第3回 健康な食事パターン
2011年4月記事 vol.83 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第3回 健康な食事パターン今回も、2010年版アメリカ人の栄養ガイドラインの概要を報告する。第3章「健康な食事パターン」では、具体的に地中海式食や野菜・果物中心のベジタリアン食などの効用について紹介している。 高血圧予防には、野菜・果物に全穀物に低脂肪食 2010年版アメリカ人の栄養ガイドラインの第3章では、健康な食事のパターンを具体的に示している。 まずは、米国立衛生研究所(NIH)が推奨する高血圧予防の食事。 野菜・果物、低脂肪の牛乳及び乳製品、全穀物、鶏肉、魚類、ナッツをよく食べ、赤身肉や加工肉、塩分や糖分、糖分入り飲料水を控えめにする。また、飽和脂肪、コレステロールを少なめにし、カリウム、マグネシウム、カルシウム、蛋白質、食物繊維を多く摂るというもの。 同様な食として、DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 食も挙げている。 これは、野菜・果物、低脂肪 […]
-
 2011年3月記事 vol.82 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第2回 栄養摂取量の増減
2011年3月記事 vol.82 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第2回 栄養摂取量の増減前回に続き、2010年版アメリカ人の栄養ガイドラインの概要を報告する。第2章「栄養摂取量の増減」では、健康な食生活のために、「取り入れたほうがいい食品」「除いたほうがいい食品」に分類し、それぞれ紹介している。 推奨食品は、野菜・果物、魚、全穀物 2010年版アメリカ人の栄養ガイドラインで、健康な食生活のために推奨しているのが、野菜・果物、魚、全穀物。 中でも、1日に少なくとも2カップ半の野菜または果物は、心臓発作や脳卒中のリスクを軽減するとし、摂食を重視している。 また、穀物の少なくとも半分は全穀物で摂る。無脂肪または低脂肪の牛乳や乳製品の摂取量を増やす。たんぱく質は、魚、鳥肉、卵、大豆など、さまざまな食材から摂るようアドバイスしている。 この他、カリウム、食物繊維、カルシウム、ビタミンDを豊富に含む食品の摂取、50歳以上の場合は、ビタミンB12を多く含む食品の摂取を勧めている。 限りな […]
-
 2011年2月記事 vol.81 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第1回 カロリー制限と運動で肥満撲滅へ
2011年2月記事 vol.81 「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」公表 第1回 カロリー制限と運動で肥満撲滅へ1月31日、「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」が発表された。アメリカ人の健康管理のために、最新の栄養分析などに基づき5年ごとに改訂されるもので、2010年版は「肥満対策」「栄養摂取の増減」「健康な食事パターン」の3章で構成されている。今回より3回に分け各章の概要を紹介する。 「肥満」が深刻化、ガイドライン1章全てが肥満対策 米国で、どれほど「肥満」が大きな社会問題となっているか、先頃発表された「2010年版アメリカ人の栄養ガイドライン」をみれば誰もが納得がいくだろう。なんと、1章全てが肥満対策に割かれている。 昔から、「大きいことはいいことだ」とばかり、アメリカ人は何もかもビッグサイズを好んだ。 食事の皿もソーダのコップも、とにかくビッグ。レストランの食事も山盛りで、当然胃袋も大きくなる。 「食べ過ぎ+運動不足=肥満」という図式が生活に定着している。 肥満に至った構図は実に明白 […]
-
 2011年1月記事 vol.80 ストレスで睡眠障害を訴える米国民が増加
2011年1月記事 vol.80 ストレスで睡眠障害を訴える米国民が増加米国では長引く景気低迷からストレスを抱える人々が急増していることを以前伝えたが、身体的な影響では鬱や睡眠障害といった症状で現れるケースが多い。今回は睡眠障害に焦点を当て、現状や代替医療での対策についてまとめてみた。 睡眠障害による医療費、年間で160億ドル 疾病管理予防センター(CDC)の統計によると、米国で総人口の4分の1ほどが「たまによく眠れないことがある」と訴えており、人口の約10%が慢性的な不眠症に苦しんでいるという。 全米ヘルス統計センターの2002年ナショナル・ヘルス・インタビュー調査(NHIS)では、調査対象の17.4%が過去12カ月間に不眠などの慢性的な睡眠障害に悩まされていると回答している。 そのうち大半が不安や鬱、慢性的な心臓疾患、糖尿、高血圧、肥満といった疾患を抱えていた。 睡眠障害は、仕事や車の運転、社会生活、生活の質にマイナスの影響をもたらすだけでなく、病気発症 […]
