ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2010年12月記事 vol.79 米国民の健康10年指針、「ヘルシーピープル2020」公表
2010年12月記事 vol.79 米国民の健康10年指針、「ヘルシーピープル2020」公表12月に、今後10年間にわたるアメリカ人の健康づくりをまとめた「ヘルシーピープル2020」が米国保健社会福祉局より公表された。10年ごとの見直しで、米国健康政策の指針となるものだが、理想を高くかかげ過ぎた2010年版を教訓に、2020年版は現状に即した目標設定となっている。 1979年、国をあげて健康づくりに着手 米国が国をあげて包括的な健康向上・疾患予防計画に乗り出したのは1979年。 米保健福祉局(HHS)が中心となり、乳児、子ども、未成年、成人、高齢者の5ライフステージ別に目標を設定した「ヘルシーピープル」を公表した。 翌80年には「健康向上・疾患予防――国の基本方針」を発表、乳児の死亡率を35%減少するなど、さまざまな健康項目ごとに具体的な目標値を掲げ、健康づくりに関する初の10年計画を打ち出した。 そして、これらを土台に、政府当局や専門家らはさらに議論を重ね、1990年に「ヘル […]
-
 2010年11月記事 vol.78 米国で極度のストレスを訴える人々が増加
2010年11月記事 vol.78 米国で極度のストレスを訴える人々が増加長引く不況の影響などで、体調を崩すほどの強いストレスを感じているアメリカ人が増えている。しかも、調査によると、大人たちのストレスが家族におよび、子供たちまでイライラや不眠を訴えているというから事は深刻だ。ストレスに病む米国の実体を報告する。 米国民の44%、過去5年でストレスが悪化 米国民の3分の1が極度のストレスに—。米国心理学協会の最新調査で、精神不安を抱える人々が増加していることが分かった。さらに、親の強いストレスが子供たちにまで波及している実体が明らかになった。 調査は2010年8月3日-27日、米国在住の18歳以上の大人1,134人(8歳から17歳の子供を持つ大人100人を含む)を対象に、同協会の依頼で世論調査会社大手のハリス社が実施。 それによると、米国民の44%が過去5年間でストレスがひどくなっていると回答。32%が体調不良を自覚するほどの極度のストレスを感じて […]
-
 2010年10月記事 vol.77 米国女性がん死因2位の乳がん、検診に新基準浮上
2010年10月記事 vol.77 米国女性がん死因2位の乳がん、検診に新基準浮上米国では、10月は乳がんの予防月間。乳がんは女性のがん死因の2位に付いているだけに、検診や予防に多くの関心が集まる。乳がん検診といえば、マンモグラフィー(乳房X線撮影)による早期発見で生存率が高まるといわれているが、定期検診の開始年齢をこれまでの40歳から50歳に引き上げてはどうか、という新基準も浮上している。 米国女性、8人に1人が乳がんに罹患 米国立衛生研究所(NIH)によると、米国で女性の乳がん罹患率は8人に1人、がんによる死因では肺がんに次ぎ2位に付いている。今年だけでも約20万7000人の女性が新たに乳がんと診断され、約4万人が死亡するものと推定されている。 がん対策では検診と予防が車の両輪に例えられる。ふだんの食事などでの予防は後述するとして、米国では10月は乳がん予防月間、まずは乳がん検診の現状から。 乳がんは皮膚がんと並び最も診断しやすいがんといわれている。 早期発見で転 […]
-
 2010年9月記事 vol.76 米国栄養ガイドライン、2010年度版が年末に公表
2010年9月記事 vol.76 米国栄養ガイドライン、2010年度版が年末に公表2005年、アメリカ人の栄養指針である栄養ガイドラインが公表された。5年毎の改訂のため、今年度末には2010年度版が出ることが予定されている。05年度版では、初めて全穀物の有用性が明示、また魚類の摂食が推奨されたが、はたして目標とする理想の「食」は国民に浸透したのか。10年度版の発表に先駆け、アメリカ人の食生活の現状を報告する。 現実はガイドラインとかけ離れた食生活 2005年版栄養ガイドラインでは、成人の1日の理想的な摂取カロリーを2000とし、1日にそれぞれ、野菜2.5カップ、果物2カップ、穀物6オンス(約170g)、ミルク3カップ、肉と豆類を5.5オンス(約156g)の摂取を推奨している。 塩分については2300mgに控えれば、高血圧の心配はないとしている。 アメリカ国民の多くが野菜や果物、穀物が体に良いのは十分知っているし、塩分の摂り過ぎが体に悪いこともよく知っている。 しかし、 […]
-
 2010年8月記事 vol.75 米国がん協会、がん撲滅で2015年計画公表
2010年8月記事 vol.75 米国がん協会、がん撲滅で2015年計画公表米国ががん撲滅に乗り出して今年で39年目を迎える。国をあげての取り組みが奏功したのか、がん罹患・死亡率とも減少傾向にある。さらに拍車をと、米国がん協会では、がん撲滅2015年計画を公表した。米国のがん罹患・死亡者の現状とがん撲滅の取り組みを報告する。 2010年、米国で153万人が新たにがんを発症 2010年、米国で新たにがんと診断される患者は152万9560人、うち男性が78万9620人、女性が73万9940人。がんによる死亡者数は、男女合わせると56万9490人—。 今年7月、米国がん協会が機関誌「がん統計2010」に掲載したがん罹患・死亡者の推定人口である。 がん発症の内訳では、多い順から、男性が、前立腺がん(21万7730人)、肺がん(11万6750人)、大腸がん(7万2090人)。女性では、乳がん(20万7090人)、肺がん(10万5770人)、大腸がん(7万480 […]
-
 2010年7月記事 vol.74 医療費の削減目指し、予防ケアの新法が成立
2010年7月記事 vol.74 医療費の削減目指し、予防ケアの新法が成立世界の先進国の中で、最も医療費が高いといわれる米国。年々高騰する医療費の歯止めには、まず予防が大切と、政府も予防ケアの整備に乗り出した。その一環として、サプリメント・栄養療法などの補完・代替医療についても注目している。米国における医療費削減対策の現況を報告する。 総医療費は対GDP比17.3%、先進国中トップ 個人の破産申告の半数以上が医療費がらみ。医療費の支払い不能が原因で破産者が続出。 世界№1の先進国、米国の話である。 生活者の医療費負担はもはや深刻の極みに達している。重い病気にかかった場合、たとえ医療保険に入っていたとしても、よほどの蓄えがない限り、「破産」とは決して無縁ではない。それが米国の実状である。 そうした、米国の生活者の医療費負担にあえぐ実態が目に浮かぶような数字が公表された。 The office of the Actuary of the Centers for M […]
-
 2010年6月記事 vol.73 米国で増える自閉症児、求められる代替医療
2010年6月記事 vol.73 米国で増える自閉症児、求められる代替医療米国をはじめ世界中で患者が増えているといわれる自閉症。近年米国では、この病名に「スペクトラム(連続体)」という言葉が付き、これまで自閉症とみなされなかった軽度の症状までも自閉症と診断されるようになった。米国における自閉症の発症率や代替療法利用率など現状を報告する。 90年代初頭、「自閉症」に新たな診断基準 「自閉症スペクトラム」は社会や人とのコミュニケーション能力に問題がみられる発達障害の一種で、知的・言語障害を伴わない高機能自閉症(アスペルガー症候群)なども含まれる。 「スペクトラム(連続体)」という呼称は、病状が多彩で、軽度から重度までの境界線が虹のように曖昧であることに由来する。 疾病対策予防センター(CDC)の推計によると、米国の子供の110人に1人が、「自閉症スペクトラム」を発症しているという。患者は0歳-21歳で、推定で約73万人。 ちなみに、米国の子供の約13%が、軽度から […]
-
 2010年5月記事 vol.72 老人から子供まで、米国で増える関節炎
2010年5月記事 vol.72 老人から子供まで、米国で増える関節炎米国で最も罹患率の高い病気の一つである関節炎。・・・関節リュウマチって、子どもにも発症するの?そうしたさまざまな疑問に答えるため、5月は米国で関節炎への認識と理解を深める月間に指定されている。米国の関節炎最新情報を報告する。 成人の5人に1人が関節炎、子どもの250人に1人が関節リュウマチ 米国疾病対策センター(CDC)の統計によると、米国における関節炎患者は推定で約4600万人。罹患率でみると、成人の5人に1人とかなり高い。 さらに高齢者人口の増加で、2030年には6700万人に膨れ上がるものと予想されている。 関節炎は、関節の炎症をともなう疾病の総称で、変形性関節炎を筆頭に、関節リュウマチ、狼そう、線維筋痛、通風など病名は100を超える。 症状は局所だけでなく全身にもおよぶ。発赤、腫脹、圧痛、こわばり、可動域制限、全身では発熱、全身倦怠感、体重減少などの症状がある。 関節リュウマチは […]
-
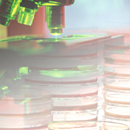 2010年4月記事 vol.71 米国立衛生研究所(NIH)の栄養補助食品室(ODS)、 サプリメント研究に注力、5ケ年計画を発表
2010年4月記事 vol.71 米国立衛生研究所(NIH)の栄養補助食品室(ODS)、 サプリメント研究に注力、5ケ年計画を発表米国で年間売り上げ250億ドルといわれるサプリメント市場。現在、ビタミン・ミネラルやハーブをはじめ少なくとも5万種類のサプリメントが米国市場に出回っている。4月初旬、米国立衛生研究所(NIH)の栄養補助食品室(ODS)が5ケ年計画を発表した。サプリメントの研究支援や情報提供にさらに力を入れる構えだ。 ODSの5ケ年計画、サプリメントの分析・評価など4つのゴールを掲げる ODSは4月初旬、5ケ年計画(2010-2014)を発表した。 計画書の冒頭で、ディレクターのポール M.コアテス氏はこう語っている。 「ODSのミッションは、サプリメントへの知識と理解を深めていくこと。そのために、研究を支援し、科学的情報を評価、研究報告を広め、生活の質と健康の向上を目指し、一般消費者の教育に力を入れている。この揺るぎないミッションのもとに、新たに浮かび上がった重要な課題を取り上げ5ケ年計画の目標と方針を […]
-
 2010年3月記事 vol.70 ハーブをめぐる誤報道に、関連団体が批判
2010年3月記事 vol.70 ハーブをめぐる誤報道に、関連団体が批判米国では90年代に入り、国民の間で代替医療を求める機運が高まる。サプリメント・ハーブによる栄養療法やカイロプラクティクス、ヨガなどが注目を浴びるようになった。しかし、時に代替療法についての誤った報道をめぐり、関連団体が報道機関に批判の矛先を向けるような場面も。ハーブをめぐるメディア報道など近況を報告する。 米国ボタニカル協議会、正確なハーブ報道を要請 「ハーブやハーブサプリメントの安全性などについて医療関係者や一般消費者に向けて、医学誌に少なくとも年に何度か記事が掲載される。しかしその中で、ときおりハーブに関してきちんとした知識もなく書いている人の記事が掲載されていることがある」 そんなふうに、今年2月、米国ボタニカル(植物)協議会が批判したのが、the American College of Cardiology誌に掲載された記事。協議会では、記事の内容が誤りだとし、数か所を指摘した。 […]
-
 2010年2月記事 vol.69 サプリメント・ハーブなど、子供の代替療法利用が盛んに
2010年2月記事 vol.69 サプリメント・ハーブなど、子供の代替療法利用が盛んに米国で子供たちの代替療法の利用が増加している。親の影響もさることながら、既存医療と組み合わせた統合医療を勧める小児科医が増えているためだ。利用の現状、奨励団体、最新研究など、子供たちを取り巻く状況を報告する。 18歳以下の利用者は約870万人、ADHDなどの症状緩和に 米国小児科学会(AAP)の機関誌「Pediatrics」(電子版、2010年1月25日付け)に、子供の代替療法(Complymentary and Medicine、以下CAM)の利用状況をまとめた報告書が掲載された。 2007年National Health Interview Surveyのデータをもとに18歳以下の子供たちのCAMの利用状況を分析、子供対象の貴重な資料として注目されている。 同研究報告によると、米国で18歳以下、総人口の11.8%にあたる約870万人が、ビタミンを除くCAMを利用しているという。 また […]
-
 2010年1月記事 vol.68 オバマ政権、加齢研究に予算援助
2010年1月記事 vol.68 オバマ政権、加齢研究に予算援助50歳前後のベビーブーマー(団塊)世代の「若返り願望」に応え、米国では加齢をテーマにした研究が花盛りだ。オバマ政権の予算援助で加齢研究にますます拍車がかかっている。高齢化社会を迎え、高齢者の疾患に対応する栄養成分の研究にも期待がかかる。 米国立加齢研究所(NIA)、加齢研究で新予算 2009年2月、オバマ大統領の署名を得て、米国経済再生・再投資法(ARRA)が新法として成立した。 ARRAには、雇用の維持・創出、失業者への経済援助、さらに科学研究の支援まで盛り込まれている。 ARRAの成立で、米国立衛生研究所(NIH)には、今後2年間にわたり研究および設備投資費として104億ドルが割り当てられる。 NIHの傘下にある米国立加齢研究所(NIA)。1974年、メリーランド州ボルチモアに設立され、加齢研究で最先端をいくNIAにも2億7300万ドルのARRA予算が割り振られた。 NIAは、アルツ […]
