ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2005年12月記事 vol.19 健康と環境の健全化目指す 米国で高まるロハス志向
2005年12月記事 vol.19 健康と環境の健全化目指す 米国で高まるロハス志向アメリカで、「ロハス(LOHAS)」志向の生活者が増えている。ロハスとは、「健康と環境に配慮したライフスタイル」の意。ロハス志向の消費者は、人の健康や地球の環境を重視する企業の商品を好んで購入する。最新情報を報告する。 アメリカ人の約30%がロハス志向、市場規模2290億ドル 「ロハス」とは、Lifestyle Of Health And Sustainabilityの略。ロハス志向の人々は、とくに「健康や環境」を第一に考え、購入する商品を選び、健全なライフスタイルを目指す。アメリカで、「ロハス」という言葉の認知度はまだ低いが、そのコンセプトはしっかりと消費者の間に浸透しつつある。 「ロハス」の概念はアメリカで生まれた。1998年、社会学者のポール・レイ氏と心理学者のシェリー・アンダーソン氏が13年間の調査から、健康や環境を重視した生活者が増えつつあることに着目。これを「カルチャー・クリ […]
-
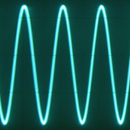 2005年11月記事 vol.18 音楽の癒し効果、医療現場で活用 ミュージックセラピー(2)
2005年11月記事 vol.18 音楽の癒し効果、医療現場で活用 ミュージックセラピー(2)いつの時代も、人々の心を癒し、慰めてくれるのは音の奏でるメロディーであった。近年、現代医学も音楽の癒し効果に着目し、積極的に医療現場での活用を試みている。米国における音楽療法の最新情報を報告する。 1950年代にアメリカで音楽療法の専門機関が発足 音楽療法の一環として、「モーツアルト効果」という言葉がブームになったのは、まだ記憶に新しい。1993年、Natureに掲載されたUniversity of California, Irvine(UCI)の研究者グループによる研究が一躍スポットライトを浴びた。UCIの学生36人にモーツアルトのソナタを聞かせたところ、試験でIQが8~9ポイント上がったことが判ったという。 最近、米国では大病院をはじめ、養護ホームやリハビリテーションセンター、ホスピスなどで、音楽セラピストによる療法が盛んに行われている。 セラピストを養成する動きも活発で、Ameri […]
-
 2005年10月記事 vol.17 アメリカ生まれのカイロプラクティック 腰痛から精神疾患まで幅広い効用が期待
2005年10月記事 vol.17 アメリカ生まれのカイロプラクティック 腰痛から精神疾患まで幅広い効用が期待首の骨や背骨が歪むと腰痛や肩凝りなどさまざまな症状が生じる。カイロプラクティックはそうした歪みを矯正することで、身体の不調を取り除く。腰痛から児童の注意欠陥・多動性障害(ADHD)といった精神疾患まで幅広い効用が期待できるというアメリカ生まれの治療術、カイロプラクティック。最新情報を報告する。 アメリカでカイロの資格を持つドクターは約6万人 ギリシャ語で「カイロ」は「手」、「プラクティック」は「施す」の意。カイロプラクティックは、手を使い背骨の歪みを正常な位置に戻すことで神経の圧迫を取り除き、人間が本来持っている自然治癒力を高め、健康を回復させるというものだ。 脳から出ているさまざまな神経は背骨のすきまから体の各組織へと繋がっている。そのため、背骨がずれると神経が圧迫され自然治癒力が低下し、痛みや、こり、しびれといったさまざまな症状が生じる。また、自律神経系へも影響を与え、ホルモン分泌な […]
-
 2005年9月記事 vol.16 治療を促進するプラセボ効果
2005年9月記事 vol.16 治療を促進するプラセボ効果見た目は薬剤だが、中身は全く別物。こうした偽薬を服用させることで身体に生じる変化をプラセボ(placebo)効果と呼ぶ。現在、プラセボは、医療現場において、患者の精神的ケアに、また、薬剤の治験の際などに利用されている。患者の精神状態をポジティブな方向へと導き、症状の改善を促進するプラセボ効果とは。 活性成分を含まない偽薬に被験者が反応 「薬を飲んで症状は良くなったが、後から聞いたら実は偽薬だった」などという話を耳にする。これが、プラセボ効果である。 プラセボという言葉はラテン語で「喜ばせる(I shall please)の意味。古代医学、また民間療法では、ミイラ薬、蜂の巣、クモの巣、蟻、その他骨や歯の粉末などが使われたといわれる。外見上では本物の薬 と区別のつかない、いわゆる偽薬で、現在ではシュガーピルなどが用いられている。 活性成分を含まない偽薬によるプラセボ効果を最初に報告したのはハ […]
-
 2005年8月記事 vol.15 エビデンスに裏付けられた鍼の効果
2005年8月記事 vol.15 エビデンスに裏付けられた鍼の効果「腰がいたい」「頭がいたい」「疲れがとれない」といった不調な時、鍼に助けを求める アメリカ人が増えている。ツボや気血といった用語も、「acupuncture points(ツボ)」「Qi(気)」とすでに英語になっているほどだ。最近では健康ばかりでなく、美容効果も注目されている。エビデンスに裏付けられた 鍼の効き目とは……。 鍼治療のメカニズム 東洋医学では、人間の体には2000ヶ所を超える「ツボ」があるといわれている。ツボは、心身の健康を司るエネルギー「気血(きけつ)」の通り道「経絡(けいらく)」の上に点在する。 この経絡を気血がスムーズに流れていれば健康を保てるが、逆に滞ると変調をきたし、病気になる。そこで、症状にあったツボを鍼で刺激し気血の流れを整え ることで、頭痛や関節炎といった不調や病気が治るというわけだ。ツボを刺激すると、経絡を通じて脳や脊髄に刺激が伝わ […]
-
 2005年7月記事 vol.14 血圧低下から免疫促進まで幅広い効用 ユーモアセラピー
2005年7月記事 vol.14 血圧低下から免疫促進まで幅広い効用 ユーモアセラピー「人間は笑う力を授けられた唯一の動物である」(F・グレビル)――人間だけに授けられた笑い、それには何らかの意味があるはずである。今、アメリカでは「笑い」がもたらす心身への治癒が注目されている。「笑いの療法」による最新の研究成果を報告する。 13世紀、手術の痛み軽減のため医療現場でユーモアセラピー ソロモン王時代、既に笑いの癒し効果は認められていたという。聖書の箴言の中にもその一文が見られる。13世紀には、手術による痛みを軽減するため外科医が治療現場にユーモアセラピーを取り入れることを図ったともいわれる。 そして、近代医学の中で、20世紀になって笑いの治癒力をテーマにした科学的研究が盛んになり、応用されるようになった。ユーモアセラピーを有名にしたのが、ノーマン・カズンズ氏である。彼は膠原病を克服したが、その殆どの要因が、喜劇や面白いものを見て笑ったことだと、自ら語っている。 思いっきり笑っ […]
-
 2005年6月記事 vol.13 音楽は魂のクスリ、研究で効果が実証 ミュージックセラピー
2005年6月記事 vol.13 音楽は魂のクスリ、研究で効果が実証 ミュージックセラピー情緒のカタルシスに音楽が有効である――と、音楽の効用を説いたのは、ギリシャの哲学者アリストテレス。また、古代エジプト人は音楽を「魂のクスリ」とよんでいた。そして今、ストレスを解消し、免疫力を高めると、音楽の幅広い効能が心と体のセラピーとして注目を集めている。アメリカでのミュージックセラピーの現況を報告する。 精神病院慰問の慈善活動で用いられたのがはじまり ミュージックセラピー(音楽療法)は、ストレスなどで病んだ心や体の症状を改善したり、痛みを緩和し生活の質の向上を図る目的で音楽を用いる療法。ただ聴くだけでなく、歌ったり、演奏したり、踊ったりするなど能動的な方法もある。 自分の好みやその時々の心と体の状態にあった音楽を聴いてリラックスしたり、元気になったり、そんな利用法ももちろんあるが、基本的には専門知識を持った音楽療法士が行う治療法だ。実際に医療現場では下記のような治療に音楽療法が使われ […]
-
 2005年5月記事 vol.12 香りでストレスケア、医療にも応用 アロマセラピー
2005年5月記事 vol.12 香りでストレスケア、医療にも応用 アロマセラピーアメリカで毎年2ケタの売上率を伸ばしているアロマセラピー。美容と健康の両面で人気を集めているが、ここ最近、医療目的での利用が増えているという。アメリカで人気の精油とその働きなどをまとめてみた。 クレオパトラも香りのパワーを活用 アロマセラピーは、芳香植物(ハーブ)から蒸留法や圧搾法によって抽出した天然の精油を使い、その芳香成分のもつ薬理作用を利用して心身の病気を治療する「植物療法」のこと。ラベンダーやペパーミントの香りをかいでストレスケアに活用したり、最近では炎症を抑えるなどの医療行為としても注目されている。 「香りのパワー」の歴史は古い。絶世の美女といわれるクレオパトラは、室内にバラの花びらを敷き詰めて、そのアロマで男性を魅了したとか。 それはさておき、植物療法は何千年も前から世界のさまざま な地域で利用されていたが、「アロマセラピー」という言葉ができたのは1937年。名付け親は、フラ […]
-
 2005年4月記事 vol.11 医療現場でも効能に注目 アニマルセラピー
2005年4月記事 vol.11 医療現場でも効能に注目 アニマルセラピーペットとしての動物の存在は、人間にとって欠かせないものとなっている。家族として、また友人として、ペットが人間に与える癒しは、計り知れないほど大きい。アメリカでは、動物との接触による療法は、アニマル・アシステッド・アクティビティーズ(AAA)、ペットセラピー、アニマル・アシステッド・セラピー(AAT)、ドッグセラピーなどさまざまに呼ばれ、積極的に取り入れる医療現場も増えている。現況を報告する。 精神的ダメージを受けた子どもに対する療法としても注目 アメリカで、初めて動物が治療に使われたのは1944年といわれる。イギリスではさらに遡って1792年、精神的疾患患者にウサギや鶏を使ったのが始まり。今では、心臓病、高血圧からエイズ、がんといったあらゆる疾患の治療現場で、訓練された動物が提供されている。 そうしたサービスの提供でよく知られる団体、Delta Societyによると、アメリカを始めとす […]
-
 2005年3月記事 vol.10 米国で代替医療の中核 カイロプラクティック療法の現況
2005年3月記事 vol.10 米国で代替医療の中核 カイロプラクティック療法の現況カイロプラクティック(Chiropractic)は、ねじり、引く、押すなどの動きを脊柱に加え、背骨やその関節を矯正する治療法で、身体が持つ本来の自然治癒力を高めようという理論に基づいている。1800年代後半、米国アイオワ州で誕生したといわれるが、こうした療法は古代エジプト時代よりみられたといわれる。米国で代替医療の中核を担うカイロプラクティック療法の現況を報告する。 米国民の12~15%がカイロプラクティックを受ける 米国におけるカイロプラクティックの創始者といわれるD・D・パーマーはこの治療法に呼び名を付けるに当たって、ギリシャ語で手を意味するカイロ、そして技術という意味のプラクティコスを使った。 米国では現在、ベビーブーマー世代が中高年を迎え、加齢による身体の不調への対処を代替療法に求める傾向が強まっている。特に、年齢と共に増す身体の節々の痛みに対しカイロプラクティックの需要が急増し […]
-
 2005年2月記事 vol.9 米国で再び脚光浴びるホメオパシー
2005年2月記事 vol.9 米国で再び脚光浴びるホメオパシーいわば毒をもって毒を制す—ホメオパシー療法が今、米国で見直されている。治療対象となる疾患と同じような症状を起こす物質をごく少量投与し、患者の抵抗力・自然治癒力を高めていくという療法だ。米国で、今またホメオパシー・ブーム再燃の波が押し寄せている。 悪い症状を押し出す根本療法 ホメオパシーの「ホメオ」は「似たもの」、「パシー」は「病気」という意味。ホメオパシーは同種療法、類似療養ともいわれる。症状を起こすものは、その症状を治せるという原理に基づいた療法だ。 たとえば、風邪の際の咳きや吐き気などの症状をとりたい場合は、患者にイペカックという逆に吐き気をもよおすホメオパシー薬を与える。イペカックは南米原産のアカネ科の低木で、健常者が服用すると、咳きや猛烈な吐き気を伴う。 ホメオパシー薬は、直に投与すれば症状はますます悪化してしまうものを、極限まで薄めて極少量与える。一時的に症状が悪化 […]
-
 2005年1月記事 vol.8 米国にハーブ旋風巻き起こした アンドリュー・ワイル博士の功績
2005年1月記事 vol.8 米国にハーブ旋風巻き起こした アンドリュー・ワイル博士の功績高額な医療費、面倒なケアシステム、そうした現代医学にためらいをみせるアメリカ国民が代わりに選んだ医療は…。代替療法(alternative medicine)と呼ばれるもう一つの医学、伝統伝承医療であった。中でも、日頃の食事による栄養療法は手軽な療法として予防医学の中軸となっているが、とくにハーブ・サプリメントを用いた療法は他の療法に比べ自己のペースで容易に行えることから人気が高い。そうしたハーブの効能をアメリカに知らしめ、90年代に入って一大ハーブ旋風をもたらしたのがアンドリュー・ワイル博士。アメリカで知らない人はいないとまで言われるハーブ療法の権威である博士の功績とハーブ療法の概要を報告する。 ワイル博士のHP、週に50万ヒット 2002年にハーバード大学が行った調査で、アメリカ人の35%が代替療法を利用しており、その割合はさらに増加の一途をたどっていることがわかった。 そして、昨年 […]
