ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2016年12月号記事 vol.151 1日1箱の喫煙で肺に年間150個の遺伝子変異
2016年12月号記事 vol.151 1日1箱の喫煙で肺に年間150個の遺伝子変異喫煙は肺やその他の臓器の著しい遺伝子損傷に関連することが、米ロスアラモス国立研究所(ニューメキシコ)のLudmil Alexandrov氏らの研究でわかり、論文が「Science」11月4日号に掲載されました。 研究の結果、1日1箱のタバコを吸う人では、肺に毎年平均150個の余剰な突然変異が起きることが判明しました。これにより喫煙者の肺がん発症リスクが高い理由の説明がつきます。身体の他の部分の腫瘍にも、喫煙に関連する突然変異がみられました。Alexandrov氏は、「今回の研究は、喫煙ががんを引き起こす方法について新しい洞察をもたらすものだ。われわれの分析は、喫煙が複数の別個のメカニズムにより、がんにつながる突然変異を引き起こすことを示した。タバコの煙は、直接曝露される臓器のDNAを損傷するだけでなく、直接的・間接的に曝露される臓器で細胞の突然変異の速度を早める」と述べていま […]
-
 2016年11月号記事 vol.150 歯のクリーニングで健康管理
2016年11月号記事 vol.150 歯のクリーニングで健康管理定期的な歯科検診は明るい笑顔を保ち、毎日の生活を快適にするだけでなく、様々な健康の維持にも役立ちます。今回は、口腔衛生の改善による健康管理についてご紹介します。 米バージニア・コモンウェルス大学感染症部門内科助教授のMichelle Doll氏らの新たな研究で、定期的な歯のクリーニングにより肺感染症を引き起こす細菌量が減少し、肺炎リスクが低下する可能性があることが示唆されました。 米国では毎年100万人近くが肺炎を発症し、5万人が肺炎で死亡しています。誰でも肺炎にかかる可能性はありますが、高齢者、他の肺疾患がある患者、AIDSなどの疾患をもつ患者ではさらに多くみられます。この研究では、2万6,000人超の記録をレビューしたところ、歯科医を全く受診していない人は、年2回の歯科検診を受けている人に比べて細菌性肺炎になる可能性が86%高いという結果が出ました。Doll氏は、「口腔衛 […]
-
 2016年10月号記事 vol.149 冬に風邪をひきやすい理由
2016年10月号記事 vol.149 冬に風邪をひきやすい理由科学的な裏付けはありませんが、「冬は風邪の季節」というのは、一般通念となっていますね。「Proceedings of the National Academy of Sciences」最新号に掲載された新たな研究で、冷たい空気に触れて体内温度が下がると、免疫系がウイルスを撃退する能力も低下することが示唆されました。研究著者の1人で米エール大学医学部教授のAkiko Iwasaki 氏によると、風邪の原因となるライノウイルスは中核体温である37度よりも低い33度前後でよく増殖することが以前から知られていましたが、その理由はわかっていなかったと述べています。「マウスの気道細胞をモデルとして用いて検討した結果、鼻の中程度の低い温度では、宿主の免疫系がウイルス増殖を阻止する防御シグナルを誘起できないことを突き止めた」と、同氏は説明しています。 「屋外の冷たい空気を吸い込むと、少なくとも一時的には鼻 […]
-
 2016年9月記事 vol.148 2種類の「体内時計」が睡眠周期に関与
2016年9月記事 vol.148 2種類の「体内時計」が睡眠周期に関与睡眠を遮断したときの脳の各領域の反応には、「体内時計」と「体内砂時計」がともに影響していることが新たな研究で示され、「Science」2016年8月12日号に掲載されました。ベルギー、リエージュ大学の研究グループが実施した今回の研究では、健康かつ若年のボランティア33人に42時間起きていてもらい、その間に注意力および反応時間の試験を実施し、さらにMRI検査により脳活動を記録しました。予想通り、断眠時間が長くなるほど試験の成績は低下していました。一方で、検査の結果、「概日リズム」と「恒常的睡眠欲」という2つの基礎的な生物学的プロセスの間に複雑な相互作用があることが明らかにされました。「概日リズム」は時計のようなもので、光と暗闇に反応して睡眠・覚醒サイクルを決定します。それに対して、「睡眠欲」は砂時計のようなものであり、起きている時間が長くなるほど眠りたい欲求が増大するものです。 このため、た […]
-
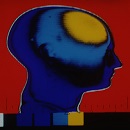 2016年8月記事 vol.147 催眠にかかったときに脳内で起きること
2016年8月記事 vol.147 催眠にかかったときに脳内で起きること催眠状態になると、本当に脳に変化が起きることが米スタンフォード大学医学部のDavid Spiegel氏らの研究でわかり、研究論文が「Cerebral Cortex」オンライン版に7月28日掲載されました。 催眠は西洋における最初の精神療法ですが、その作用はほとんど解明されていません。この試験で、Spiegel氏らは非常に催眠にかかりやすいグループ(36人)、催眠にかかりにくいグループ(20人)の合計57人を対象としました。安静時、記憶の想起時、催眠状態を惹起するためのメッセージへの曝露時に、それぞれMRI検査を実施して血流の変化を検出し、脳活動を測定しました。催眠にかかりやすい被験者では、催眠時に明瞭な脳の変化が認められ、この変化は催眠状態でないときには認められませんでした。また、催眠にかかりにくい被験者の脳でも変化は認められませんでした。Spiegel氏は、「催眠状態のとき […]
-
 2016年7月記事 vol.146 手洗いは時間をかけて丁寧に
2016年7月記事 vol.146 手洗いは時間をかけて丁寧に手洗いの際に使用する洗浄剤も、普通のせっけんのみでなく「抗菌石けん」など様々な種類のものが見られます。しかし、普通の石けんと「抗菌」石けんでは、手の細菌を除去する効果に差がないことが、韓国の新たな研究で明らかにされました。 米国食品医薬品局(FDA)によると、抗菌成分として液状石けんにはトリクロサン、固形石けんにはトリクロカルバンが用いられます。抗菌成分のトリクロサンは、細菌を数時間曝露させた場合は普通の石けんよりも強い殺菌作用が認められましたが、実際に手を洗う試験では普通の石けんを超える清浄効果は認められませんでした。韓国、高麗大学校(ソウル)の Min Suk Rhee 氏は、「トリクロサンの殺菌効果は曝露する濃度と時間によって決まる」と説明します。9時間以上継続して曝露した場合、トリクロサンには「有意に」強い抗菌性が認められましたが、10、20、30秒の曝露では、普通石 […]
-
 2016年6月記事 vol.145 暑い日の安全な過ごし方
2016年6月記事 vol.145 暑い日の安全な過ごし方救急医療の専門家が、熱波のもたらす危険について警告し、気温が上昇した日でも涼しい状態を保つ方法を助言しています。 身体は皮膚を通して、また発汗により熱を逃がして体温を調節していますが、十分に体温を下げることができなくなると、熱中症になることがあります。米ウィンスロップ大学病院(ニューヨーク州ミネオラ)救急医療部のBarry Rosenthal氏は、「高齢者や乳幼児、慢性疾患のある人は特に影響を受けやすいが、若く健康な人であっても、適切な対処をしなければ熱中症で倒れる可能性はある」と述べ、暑い時期のリスクを軽減する方法を説明しています。最良の対策は、エアコンの効いた建物の中にいることです。また、外出の際は、ゆったりとした軽く明るい色の洋服を着て帽子をかぶるか日傘を使い、露出している肌には日焼け止めを使いましょう。脱水しないように水を十分に飲むことも重要です。ただし、カフェイン、 […]
-
 2016年5月記事 vol.144 運動でがんのリスクが低減
2016年5月記事 vol.144 運動でがんのリスクが低減運動によって多くのがんのリスクが有意に低減する可能性が、大規模なレビューで示唆されました。週に2~3時間の運動をするだけでも、乳がん、大腸がん、肺がんのリスクが低減することが明らかになり、この知見は「JAMA Internal Medicine」オンライン版(2016年5月16日)に掲載されました。 今回の研究は、米国立がん研究所のSteven Moore氏を中心とするグループによって実施され、定期的な運動が13種類のがんのリスク低減に関連しているという結果が得られました。該当するその他のがんは、白血病、骨髄腫、食道がん、肝がん、腎がん、胃がん、子宮内膜がん、直腸がん、膀胱がん、頭頸部がんです。 研究グループは、米国およびヨーロッパの12件の研究データを統合し、19~98歳の成人140万人のデータベースを作成。自己申告された運動の内容によって、26種類のがんのリスクに差がみら […]
-
 2016年4月記事 vol.143 うつ病と糖尿病の併存は認知症リスクを上昇させる
2016年4月記事 vol.143 うつ病と糖尿病の併存は認知症リスクを上昇させるうつ病と糖尿病はそれぞれに脳に悪影響を与えており、併存すると認知症リスクが有意に上昇することが、「JAMA Psychiatry」オンライン版に2015年4月15日に掲載された研究結果で示されました。 50歳以上のデンマーク人240万人のデータを用いてうつ病、2型糖尿病、その両方を有する人の認知症リスクを比較したところ、登録時に対象の約20%がうつ病、9%が糖尿病、4%が両方を発症していました。登録時に認知症発症者はいませんでしたが、2007~13年の追跡中に2.4%が発症。分析の結果、他疾患や糖尿病合併症を考慮しても、認知症リスクは糖尿病によって15%、うつ病で83%、両疾患の併存で107%上昇することが分かりました。この関連は65歳未満で特に強くみられました。 研究を実施した米ワシントン大学医学部(シアトル)のDimitry Davydow 氏は「うつ病患者は糖尿病や心疾 […]
-
 2016年3月記事 vol.142 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」発表:その③
2016年3月記事 vol.142 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」発表:その③今年1月初旬、「2015年版アメリカ人のための栄養ガイドライン」が発表された。アメリカでは食生活の改善が大きな課題となっているが、ガイドラインの最新版では、健康的な食生活を実施するためのさまざまなアドバイスをおこなっている。 全穀物の摂取、理想とはほど遠い 2015年版ガイドラインによると、アメリカ人の約4分の3が、ガイドラインで奨励している野菜、果物、乳製品、オイルの摂取量を下回っている。また、たんぱく質の摂取はほぼ理想に近いが、加工肉に偏っており、魚介類が不足している。さらに、穀物も全穀物となると理想とはほど遠い。 野菜については性・年齢別を問わず十分に摂取されていない。年齢が上がるほど摂取量が増えてはいるものの、理想の量には達していない。野菜の摂取も、ジャガイモ、トマト、レタスや玉ねぎに種類が偏っている。果物も概ね理想摂取量を下回っている。また、乳製品は、幼児を除くと理 […]
-
 2016年2月記事 vol.141 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」発表:その②
2016年2月記事 vol.141 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」発表:その②今年1月初旬に「2015年版アメリカ人のための栄養ガイドライン」が発表された。その柱になっているのが、「健康的な食事パターン」。健康的な食習慣を継続することで、理想体重を保ち、高血圧や心臓疾患などの慢性病が予防できると述べている。同ガイドラインでは、「米国」「地中海」「ベジタリアン」の3種類の理想的な食事パターンのモデルを紹介している。 塩分を1日に2300mg以下に抑える 健康的な食事パターンとは、野菜・果物、穀物、低・無脂肪の乳製品、脂肪の少ない肉、植物由来のオイルをバランスよく理想カロリー内で摂取し、添加糖分と飽和脂肪はいずれも1日の摂取カロリーの10%以下、塩分は1日に2300mg以下に抑えるというものである。そして、それを実行するうえで、2015年版では、(1)食べたもの、飲んだもの全てが食事パターンに含まれる、(2)必要な栄養素は食べ物から摂る、(3)食事パター […]
-
 2016年1月記事 vol.140 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」を発表:その①
2016年1月記事 vol.140 アメリカで「2015年版栄養ガイドライン」を発表:その①今年1月初旬、「2015年版アメリカ人のための栄養ガイドライン」が発表された。今回の改訂では野菜や果物、穀物、低・無脂肪の乳製品、脂肪の少ない肉、植物ベースのオイルの摂取を奨励。また、飽和脂肪、トランス脂肪酸、砂糖、塩分の摂取を一定以下に制限している。 コレステロール摂取、1日300mg以下の制限を除外 「アメリカ人のための栄養ガイドライン」は、アメリカ厚生省と農務省により5年ごとに発行される。医師や科学者などの専門家による諮問委員会が食に関する最新の研究報告を検証して作成した報告書が基になっており、政府の栄養政策をはじめ、食品表示から学校給食、医師の患者へのアドバイスまで幅広く影響を与えている。 今回発表された第8版(~2020年)「2015年版栄養ガイドライン」は、(1)生涯を通じて健康な食生活を送る、(2)バラエティー、栄養素密度、摂取量を重視する、(3)添加糖分、飽和 […]
