ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。
最新記事
-
 2025年12月号記事 vol.259 規則正しい就寝習慣が血圧に驚くべき効果
2025年12月号記事 vol.259 規則正しい就寝習慣が血圧に驚くべき効果毎晩、同じ時刻に就寝することで血圧を改善できる可能性のあることが、新たな研究で示されました。就寝時間が不規則な人が、毎晩同じ時間に就寝することを2週間続けただけで、運動量の増加や塩分摂取量の削減と同等の降圧効果を得ることができたといいます。米オレゴン健康科学大学(OHSU)産業保健学准教授のSaurabh Thosar氏らによるこの研究結果は、「Sleep Advances」に11月17日掲載されました。研究グループは、「これは、多くの高血圧患者の血圧をコントロールするための、単純だがリスクの低い補助的な戦略になるかもしれない」と述べています。 この研究では、高血圧を有する11人の成人(男性4人、平均年齢53歳)を対象に、まずベースラインとして、1週間にわたり活動量計で就寝時間や睡眠パターンを記録するとともに、24時間の自由行動下血圧を測定しました。次に、試験参加者には2週間にわたり同じ時 […]
-
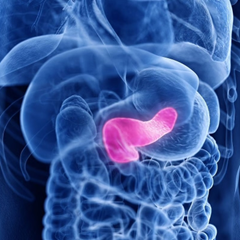 2025年11月号記事 vol.258 膵管拡張は膵臓がんの警告サイン
2025年11月号記事 vol.258 膵管拡張は膵臓がんの警告サイン膵臓がんは、進行して致命的となるまで症状が現れにくいことから「サイレントキラー」とも呼ばれています。こうした中、新たな研究で、膵臓がんリスクの高い無症状患者では、膵臓と胆管をつなぐ膵管の拡張が、がんの進行リスクを高める独立したリスク因子であることが示されました。米ジョンズ・ホプキンス大学医学部医学・腫瘍学教授のMarcia Irene Canto氏らによるこの研究結果は、「Gastro Hep Advances」に9月12日掲載されました。Canto氏は、「この知見によりがんが早期発見されれば、生存率の向上につながる可能性がある」とニュースリリースの中で述べています。 膵臓は消化酵素やインスリンなどを産生することで、消化と血糖値の調節に重要な役割を果たしています。膵臓は体の奥深くに位置するため、定期的な健康診断で腫瘍を早期発見することは難しく、診断時にはすでに進行しているケースが多いです。 […]
-
 2025年10月号記事 vol.257 帯状疱疹ワクチンは心臓病、認知症、死亡リスクの低減にも有効
2025年10月号記事 vol.257 帯状疱疹ワクチンは心臓病、認知症、死亡リスクの低減にも有効帯状疱疹ワクチンは中年や高齢者を厄介な発疹から守るだけではないようです。新たな研究で、このワクチンは心臓病、認知症、死亡のリスクも低下させる可能性が示されました。米ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の内科医であるAli Dehghani氏らによるこの研究結果は、米国感染症学会年次総会(IDWeek 2025、10月19〜22日、米アトランタ)で発表されました。 米疾病対策センター(CDC)によると、米国では3人に1人が帯状疱疹に罹患することから、現在、50歳以上の成人には帯状疱疹ワクチンの2回接種が推奨されています。帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)の既往歴がある人に発症しますが、CDCは、ワクチン接種に当たり水痘罹患歴を確認する必要はないとしています。1980年以前に生まれた米国人の99%以上は水痘・帯状疱疹ウイルスに感染しているからです。 水痘・帯状疱疹ウイルスは、数十年間にわたって人 […]
-
 2025年9月号記事 vol.256 将来的には点眼薬で老眼を改善できるかも?
2025年9月号記事 vol.256 将来的には点眼薬で老眼を改善できるかも?1日に2~3回使用する点眼薬が、将来的には老眼鏡に取って代わる老眼対策の手段となる可能性のあることが、新たな研究で明らかになりました。点眼薬を使用した人のほとんどが、視力検査で使用されるジャガーチャート(以下、視力検査表)を2、3行以上余分に読めるようになっただけでなく、このような視力の改善効果が2年間持続したことが確認されたといいます。老眼先端研究センター(アルゼンチン)センター長であるGiovanna Benozzi氏らによるこの研究結果は、欧州白内障屈折矯正手術学会(ESCRS 2025、9月12~16日、デンマーク・コペンハーゲン)で発表されました。 この点眼薬には、瞳孔を収縮させ、近見の焦点を調節する筋肉を収縮させるピロカルピンと、ピロカルピン使用に伴う炎症や不快感を軽減するNSAID(非ステロイド性抗炎症薬)のジクロフェナクという2種類の有効成分が含まれています。研究グループは […]
-
 2025年8月号記事 vol.255 歩き方を少し変えることで膝の痛みが大幅に軽減するかも?
2025年8月号記事 vol.255 歩き方を少し変えることで膝の痛みが大幅に軽減するかも?歩くときの爪先の角度を個別に修正することで、変形性膝関節症の痛みを大幅に軽減できる可能性のあることが新たな研究で示されました。また、この治療アプローチにより膝にかかる負荷が軽減され、変形性膝関節症の進行を遅らせることができる可能性があることも示唆されたといいます。米ニューヨーク大学(NYU)グロスマン医科大学のValentina Mazzoli氏らによるこの研究結果は、「The Lancet Rheumatology」に8月12日掲載されました。 Mazzoli氏は、「この研究結果は、膝関節への負荷を減らす上で最適な爪先の角度を見つけるのを手助けすることが、初期の変形性膝関節症に対処するための容易で安価な方法となり得ることを示唆している」と述べています。同氏はさらに、「この治療戦略を用いることで、患者の鎮痛薬への依存が軽減され、膝関節置換術が必要となるまでの時間を延長できる可能性がある」と […]
-
 2025年7月号記事 vol.254 悪夢は早期死亡リスクを高める
2025年7月号記事 vol.254 悪夢は早期死亡リスクを高める悪夢に関しては、「死ぬほど怖い」という表現が当てはまる可能性があるようです。悪夢を頻繁に見る人は生物学的年齢が進んでおり、早死にするリスクが約3倍高まることが、新たな研究で明らかにされました。この研究結果は、英インペリアル・カレッジ・ロンドン(UCL)の神経科学者であるAbidemi Otaiku氏により、欧州神経学会(EAN 2025、6月21〜24日、フィンランド・ヘルシンキ)で発表されました。 Otaiku氏は、「睡眠中の脳は夢と現実を区別することができない。それゆえ、悪夢を見て目が覚めたときにはたいていの場合、汗をかいて息を切らし、心臓がドキドキしている。これは、闘争・逃走反応が引き起こされているからだ。このストレス反応は、起きている間に経験するどんなことよりも激しい場合がある」と同氏は話します。 この研究では、4つのコホート研究(26〜74歳の4,196人が対象)のデータを用いて […]
-
 2025年6月号記事 vol.253 スマホ画像からAIモデルがアトピー性皮膚炎の重症度を評価
2025年6月号記事 vol.253 スマホ画像からAIモデルがアトピー性皮膚炎の重症度を評価アトピー性皮膚炎患者は近い将来、スマートフォン(以下、スマホ)のアプリに自分の皮疹の画像を投稿することで、その重症度を知ることができるようになるかもしれません。慶應義塾大学医学部皮膚科学教室・同大学病院アレルギーセンターの足立剛也氏らが、患者が撮影した画像からアトピー性皮膚炎の重症度を評価するAIモデル「AI-TIS」を開発したことを発表しました。この研究結果は、「Allergy」に5月19日掲載されました。 足立氏は、「多くのアトピー性皮膚炎患者が、自分の皮疹の重症度を評価するのに苦労している。われわれが開発したAIモデルを使えば、スマホだけで疾患をリアルタイムで客観的に追跡することが可能になり、病状管理の改善につながる可能性がある」と慶應義塾大学のニュースリリースで述べています。 研究グループによると、アトピー性皮膚炎は再発を繰り返す傾向があり、長期にわたる監視と治療の調整が必要になり […]
-
 2025年5月号記事 vol.252 好奇心は加齢に伴い減退する?
2025年5月号記事 vol.252 好奇心は加齢に伴い減退する?ある種の好奇心は、高齢になっても増していくようです。好奇心とは一般に、新しい情報や環境を学び、経験し、探索したいという欲求のことを指します。これは、個人の比較的安定した性格的な傾向としての「特性好奇心」と、特定の物事に反応して情報を得ようとする一時的な「状態好奇心」に分けられます。新たな研究では、加齢に伴い「特性好奇心」は減退する一方で、「状態好奇心」は強まることが明らかにされました。米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の心理学者であるAlan Castel氏らによるこの研究の詳細は、「PLOS One」に5月7日掲載されました。 Castel氏は、「心理学の文献によると、好奇心は加齢に伴い減退する傾向がある。」と話します。しかし、過去の研究結果の多くは、年齢と好奇心の関連を調査するにあたり、特性好奇心と状態好奇心の区別が十分に行われていなかったと研究グループは指摘します。 Ca […]
-
 2025年4月号記事 vol.251 人工甘味料スクラロースの摂取は空腹感を高める
2025年4月号記事 vol.251 人工甘味料スクラロースの摂取は空腹感を高めるカロリーゼロの人工甘味料を使用したとしても食事のカロリーが増えることはないですが、体重増加につながる可能性はあるようです。新たな研究で、砂糖の代替品は食欲と空腹感を刺激し、食べ過ぎにつながる可能性があることが明らかになりました。米南カリフォルニア大学(USC)糖尿病・肥満研究センター所長のKathleen Page氏らによるこの研究結果は、「Nature Metabolism」に3月26日掲載されました。 Page氏は、「人工甘味料として広く使用されているスクラロースは、摂取してもその甘さから予想されるカロリーを伴わないため脳を混乱させるようだ。体が、摂取した甘さに見合うカロリーを期待しているのにそれを得られない場合、時間の経過とともに、脳がそれらの物質を求める仕組みに変化が生じる可能性がある」とUSCのニュースリリースの中で述べています。 研究グループによると、米国人の約40%が砂糖の摂 […]
-
 2025年3月号記事 vol.250 たった1時間のスクリーンタイムの増加で近視リスクが上昇
2025年3月号記事 vol.250 たった1時間のスクリーンタイムの増加で近視リスクが上昇目を細めながらスマートフォン(以下、スマホ)を見つめたり、タブレットやテレビなどのスクリーンを凝視したりする時間が長くなるほど、近視になるリスクも高まることが、新たなエビデンスレビューで明らかになりました。1日当たりのデジタル機器のスクリーンを見る時間(スクリーンタイム)が1時間増えるごとに近視のリスクが高まり、近視になりやすい傾向(近視のオッズ)が21%上昇する可能性が示されたといいます。ソウル国立大学校(韓国)医学部眼科学准教授のYoung Kook Kim氏らによるこのレビューの詳細は、「JAMA Network Open」に2月21日掲載されました。 Kim氏らによると、2050年までに世界の人口の約半数が近視になると予測されているといいます。米国眼科学会(AAO)によると、近視とは、近くのものははっきり見えるが遠くのものはぼやけて見える状態のことを指し、例えば、手元の地図を確認す […]
-
 2025年2月号記事 vol.249 脂肪の多い筋肉は心疾患リスクを高める
2025年2月号記事 vol.249 脂肪の多い筋肉は心疾患リスクを高める霜降り肉のステーキはグリル料理で高く評価されますが、人間の筋肉に霜降り肉のように脂肪が蓄積していると命取りになるかもしれません。新たな研究で、筋肉中に脂肪が多い人は、心臓に関連した健康問題で死亡するリスクが高いことが明らかになりました。米ブリガム・アンド・ウイメンズ病院心臓ストレス研究室のViviany Taqueti氏らによる研究で、詳細は「European Heart Journal」に1月20日掲載されました。 この研究は、冠動脈疾患(CAD)の評価のために、2007年から2014年の間に同病院で全身PET/CT検査を用いた心臓ストレステストを受けた669人の患者(平均年齢63歳、女性70%)を対象にしたものです。PET/CT検査で左室駆出率(LVEF)、心筋血流量(MBF)、冠血流予備能(CFR)などを評価するとともに、CTで胸部の体組成として、皮下脂肪、骨格筋、筋肉間脂肪組織(I […]
-
 2025年1月号記事 vol.248 高齢者の集中力維持に最適な室温はどれくらい?
2025年1月号記事 vol.248 高齢者の集中力維持に最適な室温はどれくらい?室温は、高齢者の脳の健康に直接的な影響を与える可能性があるようです。米マーカス加齢研究所のAmir Baniassadi氏らによる新たな研究で、65歳以上の高齢者が、「集中力を維持するのが困難だ」と報告する可能性が最も低い温度は20〜24℃であることが明らかになりました。この研究の詳細は、「The Journals of Gerontology: Series A」に12月3日掲載されました。 本研究の背景情報によると、人間は、加齢とともに気温の急激な変化に対応する能力が低下します。体温を調節する能力は加齢とともに低下するものですが、慢性疾患を抱えていたり、それに対する治療薬を服用していたりする場合には、その傾向がさらに強まります。研究室ベースの研究では、周囲の温度と認知機能は因果関係にあり、極端な温度の上昇が高齢者の認知機能に悪影響を与え得ることが示されています。 この研究は、室温がどの […]
